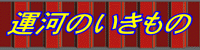わずかな水溜りで、ぴちゃっと何かが跳ねる。
水が澄むのを待って良く見ると、蚯蚓沙魚が
姿を現す。身体の色は変化が大きく、時には
明るく、時には真っ黒だったりする。どうも
棲んでいる場所によって変ってくるらしい。

|
わずかな水溜りで、ぴちゃっと何かが跳ねる。 水が澄むのを待って良く見ると、蚯蚓沙魚が 姿を現す。身体の色は変化が大きく、時には 明るく、時には真っ黒だったりする。どうも 棲んでいる場所によって変ってくるらしい。 |
|---|

|
線の入った背鰭を持つ、お洒落で小さな沙魚。 興奮したりすると、腹鰭や尻鰭の色はさらに 濃くなり、背鰭を鮮やかにきらきら輝かせる。 鰭の色や模様は平静時には薄くはっきりせず、 姫沙魚とはなかなか気付かなかった。その間 他の小型の沙魚と一色たに微倫吾(ビリンゴ) と取り敢えず呼んでいた。 |
|---|

|
より害の少ない尿素を合成して排出するので、 水の汚い所や浅い水溜りで生活できるらしい。 干潮時の水溜りなんかでつつーっと動くのが よく見られる。身体の後半に縦縞が2本あり、 尾鰭は四角っぽくて、背鰭に黄色い帯が入る。 小さいけれど見ごたえのある綺麗な沙魚。 |
|---|

|
輝いて美しい。スジハゼなんて野暮な名前で なくて、もうちょっと気の効いた名前にして あげれば良かったのに…。因みに属するのは キララハゼ属。属名の方がぴったりしている。 |
|---|

|
ずんぐりむっくりとした体つきが可愛らしい。 三浦半島から相模湾に注ぐ森戸川の感潮域が 北限とされていたらしいけれど、京浜運河の どん詰まりである高浜運河でも東京水産大学 水産生物研究会によって確認されているから、 よく探せば東京湾内に広く存在するのかも…。 |
|---|

|
さらっと流してしまいそうな見かけだけれど、 良く見ればアベハゼのように鼻先がせり出し、 丸っこい顔つきをしている。大きくなっても せいぜい3cmほどにしかならない小さな沙魚。 きっといるぞ、きっといるぞ…と思い続けて やっと見つけることができた2007年の2月…。 |
|---|
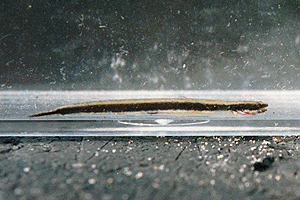
|
こいつはさらに細長く、顔つきも鋭く尖って およそ沙魚とは思えないような姿をしている。 沙魚の仲間に独特の愛嬌と言うか何と言うか、 そんなものが不足しているような気がする…。 アナジャコやスナモグリの巣穴にちゃっかり 潜り込んで暮らしているらしい。故にヒモ… ということではなさそう。 |
|---|

|
ドロメのように平たい。2008年の9月に 初めて網に入ったのを見た時はマハゼなのか ドロメなのか戸惑ったけれど、体側を見れば 粗い鱗と迷彩模様がウロハゼであるぞと主張。 |
|---|

|
なってしまうから、素人(しろうと)の素で 素魚と書いておこう。白魚にしろ素魚にしろ こんなものまで運河に棲んでいるのかという 驚きは変らない。よく混同されているけれど シラウオとは別の種類で、シロウオはハゼ科。 でも、背鰭の付き方が違うようにも見える…。 そこはまぁ、希望的記述と言うことで…。 |
|---|