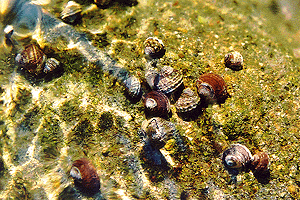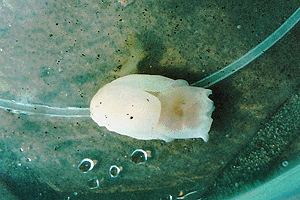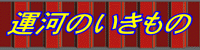寄り集まっている。殻もからからに干涸びて
死んでいるみたいだけれど、ひっくり返せば
すぐにうにゅ〜っと出て来て、また元に戻る。
そんな時には水をとことん嫌っているようで、
水の入ったバケツに入れても、いつの間にか
水の外まで這い出して、そこで動きを止める。
やがて、季節が変り秋風が吹くようになると、
少しずつ水際へ移動を始め、そのまま水際で
冬を過ごす。夏よりも活発に動き回るようで、
水底の石の表面を這い回る姿もよく見られる。
そして春一番が吹く季節になると、再び水の
上を目指して動き始める。砂の上には玉黍の
這った跡があちこちに見られるようになる。
1cmあるか無いかのごく小さな巻貝だけれど、
季節の移り変りを感じる能力は、人間よりも
遥かに優れている。