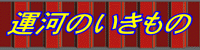たくさん付いている。もっと大きく育ったら
食べてみたいと思っている。けれど、食べる
勇気が出ないのも確か。どうしても「あたる」
という言葉が思い起こされてしまうからなぁ。
そんな訳で、運河の牡蛎を食べたことはない。
牡蛎は嫌いではなく、むしろ好きなんだけど。

|
たくさん付いている。もっと大きく育ったら 食べてみたいと思っている。けれど、食べる 勇気が出ないのも確か。どうしても「あたる」 という言葉が思い起こされてしまうからなぁ。 そんな訳で、運河の牡蛎を食べたことはない。 牡蛎は嫌いではなく、むしろ好きなんだけど。 |
|---|
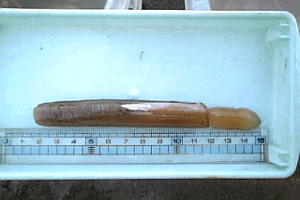
|
噴射しながら、その勢いで泳ぎまくっている。 貝の目を探して塩を振ると出てくるらしいが、 試してみたが出てこなかった。小さくて塩が 下まで届かなかったかな?。関東ではあまり 馴染みが無いけれど、食べられます。 |
|---|

|
浅蜊や潮吹きに比べると薄っぺらな体つきを しているけれど、入出水管はやけに太っとい。 しかも思いっきり長く伸びるのでその様子を 見た時は結構びびった…。 |
|---|

|
衣を透して輝いたので衣通姫と呼ばれたとか。 なるほどその殻は赤い身が透けそうなくらい 薄くてもろい。けれど皮を被った太い水管を これでもか!と言わんばかりに伸した様子は、 どちらかと言えば男性的なような気もする…。 棲む所も泥っぽい所だし…。 |
|---|

|
違って貽貝のように細い糸を出して貼り付く。 数が少なくあまり見られないのは、外来種の 貽貝類に、その生活場所を奪われているから かも知れない。 |
|---|

|
打上げられた貝殻は白いけれど、生きている うちは写真のような色の薄い幕を被っている。 食べられるかどうか知らないけれど、知らず 知らずのうちに潮吹きなんかと一緒になって いたかも知れない。 |
|---|

|
蜆の味噌汁を知らない人はまずいないだろう。 本当かどうかはさておき、肝臓に良いとされ、 呑んだ翌朝には心強い。って言うかそこまで 呑むなと言うか…。海老取川辺りでは盛んに 採られているようだから、見つかるかも…と 思っていたら、やっぱり見つかった。 |
|---|

|
感じではあるけれど、シジミ科の貝ではなく、 味噌汁の蜆の代表格である大和蜆とは縁遠い。 平成26年現在ではシオサザナミガイ科かな? |
|---|

|
小さな貝。色は白く、毛が生えているけれど 形は貽貝そっくり。だけどイガイ科ではない とのことで、だから貽貝騙しと言うことか…。 1970年代にやってきた外来種とのことで、 そんなところも外来種の多い貽貝そっくり…。 |
|---|

|
思われる欧羅巴原産の外来種。最近になって ようやく正式にウスカラシオツガイの和名が 与えられたらしい。バケツに入れておいたら、 何時の間にやら底に貼り付いていた。粘液を 分泌して貼り付くらしく、触れたらぽろりと 簡単に外れてしまった。 |
|---|