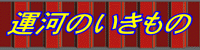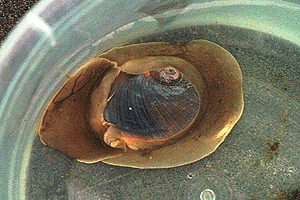
ふにゃふにゃと柔らかく、粘液でねとねと…。
それも砂地で生きてゆく為の姿形なのだろう。
事実、砂に潜るのはたいへん上手で、素早い。
浅蜊なんかの二枚貝が主食で、貝殻に小さな
穴を開けて食べる。よく波打際に穴の開いた
貝殻が落ちているのは、石牙螺貝が食べた跡。
赤螺のように殻をこじ開けたりはしない。
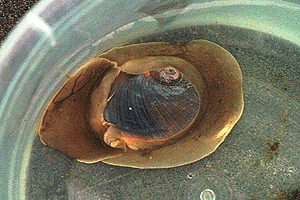
|
ふにゃふにゃと柔らかく、粘液でねとねと…。 それも砂地で生きてゆく為の姿形なのだろう。 事実、砂に潜るのはたいへん上手で、素早い。 浅蜊なんかの二枚貝が主食で、貝殻に小さな 穴を開けて食べる。よく波打際に穴の開いた 貝殻が落ちているのは、石牙螺貝が食べた跡。 赤螺のように殻をこじ開けたりはしない。 |
|---|

|
板の上半分だけが細長く伸びて、臍の中まで 巻き込まれるかのように鍵状に曲ったものは、 ホソヤツメタと呼ばれている。ツメタガイと 別種と言う程のものでもなく、地域的な差に 過ぎないらしいけれど、これだけ形が違うと 学術的なことはともかく、やはり別物として 扱いたくなってくる。 |
|---|

|
通常の石牙螺貝では殻のてっぺんがぽちっと 尖っているのに対し、こいつは尖っていない。 殻全体の高さもやや低く、扁平な感じがする。 磨耗して平らになってしまった感じでもなく、 最初からこのような形なんだろうと思われる。 |
|---|

|
産みつけられた、石牙螺貝(ツメタガイ)の 卵嚢である。見るからに奇妙な形をしている けれど、砂底に直接産みつけるには、これも きっと優れている形なのだろう。 |
|---|