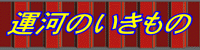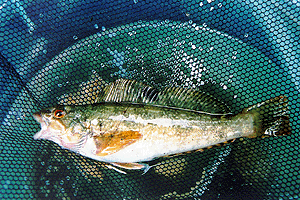
いわゆる根魚で、テトラポットに棲み付いて
いたから、泥底の運河で見つけた時は驚いた。
潮に乗って物陰を伝いながら運河へ入り込み、
そのまま取り残されてしまったのだろうか…。
夏が旬で大きいものは50cm近くなると言う。
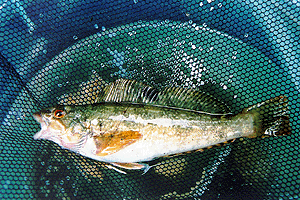
|
いわゆる根魚で、テトラポットに棲み付いて いたから、泥底の運河で見つけた時は驚いた。 潮に乗って物陰を伝いながら運河へ入り込み、 そのまま取り残されてしまったのだろうか…。 夏が旬で大きいものは50cm近くなると言う。 |
|---|

|
3文字を記した船宿の看板を見かけることが よくある。ハゼやキスと並んで、東京湾内の 釣り物としては、割と一般的な魚なのだろう。 もともと砂泥底の海域に作られた運河だけに、 見かけることは少ないけれど、幼魚を中心に 上げ潮に乗って紛れ込み、粗大ゴミや護岸の 縁なんかに付いているらしい。 |
|---|

|
釣り人の話では、以前からたまに幼魚の姿が 見られたと言う。実際にすぐ傍で釣り上げて 見せられたんじゃ、疑いようが無いことだし、 幼魚が自分の網にも入っちゃったことだし…。 さすがに棲み着いているとは考え難いけれど、 潮の具合によっては入り込んでくるのだろう。 |
|---|

|
笠子なのか目張なのか判りかねていたけれど、 身体の模様がはっきりしているし、顔つきも 下顎が前に出ているし、目の位置も低いから 目張ではなかろうかと思っている。 下の写真のものは体長7cmくらいで、活きて いるうちは、上の写真のものと同じ模様が 入っていた。ところが息絶えた途端、模様は 薄くなり始め、何時の間にか消えてしまった。 目の位置や黒い鰭からは笠子のように思える けれど、口許は下顎の方が出ているようで、 曹以のように思えなくもない。 笠子にしろ目張にしろ、防波堤の際や岩陰を 根城にしている、いわゆる根魚であることに 変り無い。鮎魚女や磯銀宝が見つかるくらい だから、運河に根魚がいても不思議ではない けれど、運河の泥だらけの底を眺めていると、 よくもこんな所まで入り込んで来たなぁ…と 感心してしまう。 |
|---|---|
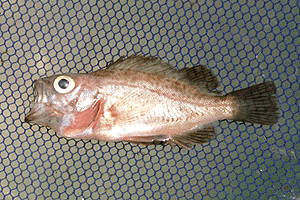
|