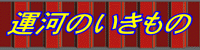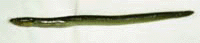
運河にもいるかも知れないな…と思っていた
けれど、何とか姿を見つけることができた…。
その名の通り泥底に穴を掘って潜んでいる魚
だから、埋立も一段落した昨今、運河の底も
それなりに安定し始めたと言うことなのか…

|
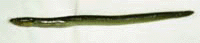
運河にもいるかも知れないな…と思っていた けれど、何とか姿を見つけることができた…。 その名の通り泥底に穴を掘って潜んでいる魚 だから、埋立も一段落した昨今、運河の底も それなりに安定し始めたと言うことなのか… |
|---|

|
その入口の運河でも鰻が見つかると言うこと。 でも目黒川や呑川に入り込んだものは、まだ 良い方なのかも知れない。この写真のものは よりによって雨水溝の中へ入ろうとしていた。 遥か南洋で産れ、やっとのことで辿り着いた 先が暗渠の雨水溝かと思うとやりきれない…。 |
|---|

|
見たらつんつん泳いでいたので驚いた。よく 見たら、竜の落し子の様な顔と、小さな鰭が ちゃんと付いていた。なるほど、首を曲げて 尻尾をくるくる巻けば、竜の落し子と言って も通用するかもしれない。痩せてるけど。 この魚がみつかったということは、運河にも 藻場があるということになるのだろうか…? |
|---|

|
「鮗」なら魚のヒイラギかと言えば、それは 誤りで、コノシロである。それならば魚類の ヒイラギはと言うと、「柊魚」と書くらしい。 沙魚釣りの外道として釣れることはまず無い けれど、から揚にしたりするとかりかりして 美味しいらしい。 |
|---|

|
横縞が何本も入った姿が、おどろおどろしい。 けれどこれでもほんの子供で、大きくなれば 2m近くになる。表層に暮らす魚で、幼魚は 流れ藻の下なんかに集る習性があるとのこと。 それらと共に湾奥まで流されてきたのだろう。 |
|---|

|
運河で鮎が見られても不思議ではないけれど、 実際にその姿を見ると、やはりいたんだなぁ と感慨に耽ってしまう。何と言っても清流の イメージの強い魚である。ちなみに東京での 解禁は例年6月1日頃。例え運河と言えども 解禁前に採取することは御法度なので要注意。 アユと言えば浜崎橋なんて橋も近いな…って これは関係ないか…。 |
|---|
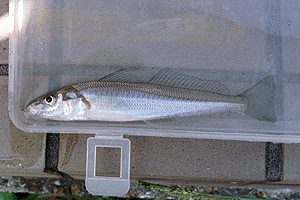
|
お馴染みの存在。色白で如何にも優しそうな 見かけをしているのに、釣れた時の手応えは 真沙魚よりも力強く、竿先を激しく震わせる。 1960年代の後半には東京湾の汚染が進み、 横須賀と木更津を結ぶ線の外側に出なければ 釣れなくなってしまったらしい。その白鱚が 再び戻って来たのかと思うと、嬉しさも一入。 |
|---|

|
とは呼ばないなぁ…。マルタッパヤと訛るか 単にマルタだなぁ…。標準和名もマルタだし。 川魚と言う印象が強いウグイの仲間だけれど、 汽水域を中心に海域まで回遊しているらしい。 たまに40cm近いものが打上げられていたり、 数cmほどの幼魚が水面を泳いでいたりする。 |
|---|

|
思われる。背鰭も2つあるし。けれど下顎に あるはずの髭には気が付かなかった。それを 確認するまでは名称未設定にしておこう…と 思いながらもう8年。まだ見つからない…。 |
|---|